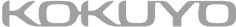コクヨデザインアワード2018
最終審査レポート
応募の4割が海外から。国際コンペとしての大きな一歩を踏み出したコクヨデザインアワード
2019年1月18日、コクヨデザインアワード2018の最終審査が行われ、グランプリ1点、優秀賞3点が決定しました。応募総数1,289点(国内766点、海外523点)のなかから、審査員の満票を得てグランプリに輝いたのは、「音色鉛筆で描く世界」(山崎タクマさん)。さらにこの作品は、トークイベントの来場者が選ぶオーディエンス賞も受賞。みごとダブル受賞に輝きました。

ファイナリストのプレゼンを公開
今年のテーマ「BEYOND BOUNDARIES」とは、境界を越える、ということ。インターネットメディアの普及、国際情勢や価値観の変化に伴って、地域、性別、文化などさまざまな境界が取り払われつつある一方、これまで潜んでいた格差や境界も新たに浮き彫りになっています。コクヨデザインアワード2018では、このテーマを通じて、身のまわりにどのような境界があるかを見つめ、デザインの力でいかにして乗り越えるか、という奥行きのある提案を求めました。

最終審査会に先立ち、挨拶する黒田英邦社長
今回ははじめて、最終審査をTHINK OF THINGS(コクヨが運営するショップ兼スタジオ)で行い、ファイナリストによるプレゼンテーションの様子を一般に公開しました。冒頭で、コクヨ 代表取締役 社長の黒田英邦は、「アワードは16回目を迎えました。ひとつのコンペにとどまらず、デザイン運動のようにもっと色々な人に関わってもらう機会にしたい。新しい展開につなげたいという思いで、今回プレゼンを皆さんとシェアすることにしました」とあいさつ。オーディエンスが見守るなか、10組のファイナリストが熱弁をふるいました。審査員たちは「どの提案もレベルがひじょうに高い」と口をそろえ、会場はポジティブな緊張感に包まれながら、密度の濃いプレゼンが次々と行われていきました。
絶賛のなか、満票で決定したグランプリ
10組の最後に登場した山崎タクマさんは、紙に鉛筆で書く時に生じる摩擦音を聴くためのペンホルダーを中心とする「音色鉛筆で描く世界」を提案しました。全盲者にインタビューをし、「これまでの文房具は視覚情報に特化したツールである」と考えた山崎さんが、鉛筆の摩擦音に着目。この音を、振動板の役割をもつPVCのペンホルダーで抽出することで、どんな人でも楽器演奏のような体験を楽しめる世界を紹介しました。山崎さんは、全盲者とワークショップを行い、実際にこれを使ってもらったといいます。「自然に、鉛筆の音だけで書いた文字を当てるゲームが生まれた。音のキャッチボールが楽しいと言ってくれました」と語ると、会場から大きな拍手がおきました。

最終審査会でプレゼンを行う山崎タクマさん
また山崎さんは、素材についてもスタディを重ねました。審査員のテーブルには、空き缶やペットボトルでつくったペンホルダーの試作が並び、最終的に汎用性を考慮したPVC製と、楽器としての佇まいをもたせたアルミ製の試作を紹介。これらの仕上げにも高い評価が集まりました。

「音色鉛筆で描く世界」はペンホルダーのほか、鉛筆削りや定規などアイテムも
プレゼンのあいだ中、審査員たちは実際にこのペンホルダーを使って紙に文字を描きながら、夢中になって音を聴いていました。「鉛筆というビジュアルを記述する道具を、音の記述に置き換えたらどうなるか。この今までにないチャレンジは、さまざまな境界を越えている」(川村真司さん)、「子どもの頃から親しんでいる文房具を使って、これほどまでに知覚が拡張するものなのか。ある意味、驚きでしかない」(鈴木康広さん)といった絶賛の声が相次ぎ、審議ではアワード史上類を見ない速さで、満票でグランプリに決まりました。
優秀賞は大ヒット商品の予感
グランプリに続いて、審査員の票を集めたのは優秀賞「スマートなダブルクリップ」(豊福昭宏さん)でした。約100年前にアメリカ人のルイス・エドウィン・バルツレーが発明して以来、形を変えることなく、不朽のデザインとして世界中で使われてきたダブルクリップ。これに対し、豊福さんは「実はこれで留められた資料は読みづらいのでは」という素朴な問いを投げかけ、100年前のデザインの更新に挑みました。紙を留める際にできる直角三角形をそのままクリップの形状にし、接合部分をスマートにすることで材料コストの削減にもつながることをアピール。審査員からは、「カドケシの再来」(佐藤オオキさん)、「身近にたくさんありながら気づかなかった視点。大ヒットしそう」(渡邉良重さん)といった、商品化への期待が寄せられました。
最終審査で「スマートなダブルクリップ」について紹介する豊福昭宏さん
同じく優秀賞に選ばれた「白と黒で書くノート」(中田邦彦さん)は、人間の視覚が持っている境界(明度を認識する差)を利用し、灰色の紙の上に黒と白のペンで文字を書くことで、それぞれの色の文字を集中して読むことができる、という提案です。ノートの紙色も、使い方に合わせて三段階の灰色を用意するなど、お客様が商品を選ぶ楽しさにも配慮しました。審査員も触発され、「白ペンで光を描けるのが新鮮。罫線のないスケッチ用のノートがあってもよいのでは」(植原亮輔さん)といった展開のアイデアが出ました。
「白と黒で書くノート」についてプレゼンする中田邦彦さん
海外からも続々と
また今年は応募総数1,289点のうち、海外からの応募が523点。ファイナリストも10組のうち4組が中国、インド、台湾の応募者で、コクヨデザインアワードが国際的にも認知度を高め、その土地や考え方の特色を生かした、完成度の高い作品が寄せられている様子がうかがえました。
インドから来日した学生ユニットSochの「Palletballet」は全審査員から高く評価された
優秀賞を受賞したインドの「Palletballet」(Soch)は、伝統的な玩具づくりの技術を生かして、子どもが絵を描くことに没頭できる、楽しくて美しい道具の提案です。また、中国の「雨花石消しゴム」(Dongguan GAFA Cultures & Creativity Institute / Jinxi Chen, Zhongbo Lu, Liangfang Fang)は、中国でお土産やお守りとして珍重される石の模様から着想し、ユーザーが使うほどに愛着が増していく消しゴムです。
ほかにも、衣服にハサミを入れるという行為を楽しむTシャツ「Cut-out T-shirt」(Shel Han)や、旅先の音を録音して送る音ハガキ「BGM」(MingHsi Chou)は、デジタル世代のデザイナーが、身体のふるまいや知覚、アナログなメディアだからこそ生まれる繊細なインタラクションに着目した提案を行い、審査員をうならせました。
(左から)MingHsi Chouさん、Shel Hanさん、Dongguan GAFA Cultures & Creativity Instituteの3人
「BEYOND BOUNDARIES」が越えたこと
受賞式後に青山スパイラルで行われたトークイベントでは、木田隆子さん(「エル・デコ」ブランドディレクター)のナビゲーションで、6名の審査員がコクヨデザインアワード2018を振り返りました。特に、提案のレベルがこれまで以上に高かったこと、海外からの応募者が増えて国際コンペとして新たな展開の予感があること、そしてコクヨデザインアワードが確実に進歩を続けているデザインコンペとして審査員自身が触発されながら審査を楽しみ、今後の発展にさらなる期待を寄せていることなどが語られました。

トークイベントで作品を公表する審査員たち
最後に黒田が次のように語り、今回のアワードを締めくくりました。「作品やプレゼンテーションのレベルの高さ、海外からのチャレンジの増加などを鑑みても、コクヨデザインアワードそのものが今回さまざまな境界を越えた、いや越えそうになっているという実感があります。当初よりアイディアをいただくだけではなく、我々自身もアウトプットすることを大事にしているアワードですので、皆さんからの提案をひとつでも多く商品化できるよう、精いっぱい取り組んでいきたいと思います。これからもっと多くの人がチャレンジする運動にまで昇華できるよう、頑張って続けていきます」。

川村真司さんがデザインしたトロフィー。メインビジュアルを立体化するように、小さな人が壁を乗り越える姿を造形。
グランプリ「音色鉛筆で描く世界」に対する審査員の講評


「全盲の方とのワークショップを通じて、文具を音色を感じ、楽しむためのツールとしての可能性を追求していく様子に、文房具の新しい扉を開け放つような印象を受けました。プロダクトの形も、通常の楽器が独特の形をしているように、使う前からいったいどんな音が出るのか想像をかきたてる魅力がある。これからの文房具のあり方について、夢を描かせてくれる提案です」(植原亮輔さん/KIGI代表、アートディレクター・クリエイティブディレクター)


「本来はビジュアル表現のために使う鉛筆をベースに、別の五感で楽しむ装置を発明するとは、とんでもなく斜め上のアイデア。その発想を、プロダクトとしても美しくてシンプルなかたちに落とし込めている。また、コンセプトの芯をぶらすことなく、定規や鉛筆削りを含めた製品群として提案できていることにも、今後の展開の可能性を大いに感じさせてくれます」(川村真司さん/Whatever クリエイティブディレクター・チーフクリエイティブオフィサー)


「テーマ設定のシャープさ、ワークショップのプロセス、プロトタイプの完成度とそこから生み出される体験。すべてにおいてクオリティが高く、アイディアを思いつきで終わらせずに、最終的にはモノとしてきちんと昇華させるという、このアワードが求めている理想形が体現されています。例えばマットブラックで統一されたカラーリング一つ取っても、元々のコンセプトである『視覚情報に頼らない』という強い意志を感じました。」(佐藤オオキさん/nendo代表、デザイナー)


「現代的な電子メディアの技術ではなく、子供の頃から親しんでいる鉛筆にシンプルな道具が付くだけのとてもアナログな方法で、新しい身体感覚を生み出し、人の潜在的な欲求に応えられていることに大きな衝撃を受けました。実際に書きながら、自分の耳がこの音を聞いているのか、鉛筆を通して身体全体が聞いているのか、体験したことのないような、身体が拡張する感じを覚えました」(鈴木康広さん/アーティスト)


「鉛筆の音がとても心地いいんです。この音を聞きたくて、プレゼンのあいだ中、描き続けていました。誰も考えたことがないような、摩擦音で文字を知覚するという発想が新しくて、今後どのように発展していくのか、期待させてくれます」(渡邉良重さん/KIGI、アートディレクター・デザイナー)


「誰の立場に立ってこだわるか。その価値をつくり、検証するプロセスが感動的でした。これだけ世の中にモノが溢れ、デジタル化も進んでいくなかで、コクヨがこれからどういう意義の元にものづくりをしていくべきなのか。背中を押されるような気持ちになりました」(黒田英邦/コクヨ 代表取締役 社長)

トークイベントでは、グランプリの山崎さんが、最終審査でのプレゼンを披露した
グランプリ受賞者、山崎タクマさんのコメント
「今回意識したのは、誰がこれを使うのか、というところ。ワークショップで得たフィードバックを製品にどうやって反映させるかを重視しました。短い時間のなかで、仮説と検証のズレを調整し、別のアイテムをつくるなど、スピーディに試行錯誤していく必要がありました。
伝わりにくいテーマだと自覚していたので、プレゼンでは、私がどういった境界を見つけて、どう乗り越え、実際にどうなったか、という一連の流れを説明するように心がけました。
オーディエンス賞の受賞は意外でした。「体験した人しかわからない」と思っていたので。ストーリーを共感してもらえたのなら嬉しいです。グランプリを受賞した時は、「やってきたことが一区切りついたのかな」と思ってホッとしました。
これは目の見えない人と一緒につくった製品です。インタビューを通じて、さまざまな課題が出て、毎日悩んであがいたので、最後に評価してもらったことに感謝しています。一方で、世の中にはまだまだたくさんの課題があります。その多くを占めているのは、健常者が日々感じているのではない部分だと思う。この作品の受賞がきっかけとなり、みんなで解決していく方向につながれば嬉しいです」

授賞式で、グランプリのトロフィーを手に喜びを語る山崎さん