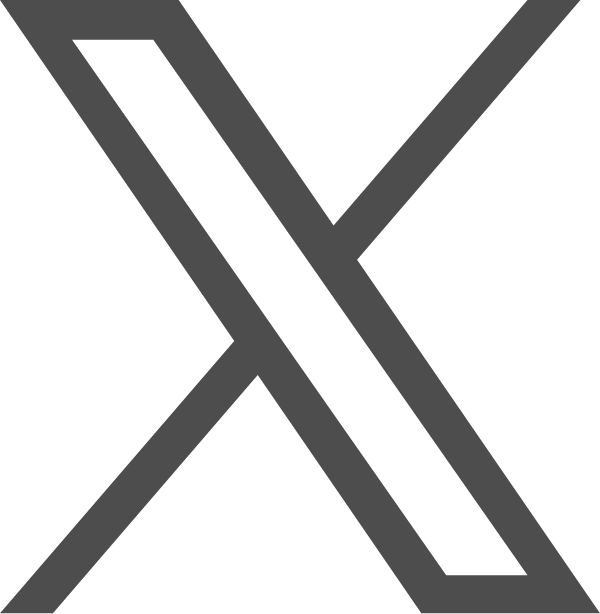ニュース
審査員インタビュー
コクヨデザインアワード2026より、新たに審査員を務めることになった森永邦彦さん。ファッションブランド「アンリアレイジ」のデザイナーとして国際的に活躍する森永さんに、お仕事の話や審査への期待を伺いました。

ファッションデザイナーの森永邦彦さん
―― 森永さんは、2003年にファッションブランド「アンリアレイジ」を立ち上げました。コクヨデザインアワードの創設が2002年。コクヨデザインアワードをご存知でしたか。
はい、もちろん。実は応募しようと思った時もありました。もともと服のデザインから始まって、その後ファッション領域におけるプロダクトデザインを手がけたこともあり、ファッション的な視点でコクヨデザインアワードに応募できないか、と考えたんです。
―― 気になるテーマがあったのでしょうか。
特定のテーマというよりは、自分の中にあった発想が形になるという点で、プロダクション(製造)のプロセスも含め、日常や人の暮らしの中に入り込めるプロダクトデザインに憧れを抱いていました。
アンリアレイジでは「日常と非日常」をテーマに服を作っていますが、ブランドの立ち上げ当初はどちらかというと非日常性のほうが強かった。それを日常とつなげてくれるのがプロダクトデザインなのではないか、と思っていました。

2009年春夏コレクション「○△□(まるさんかくしかく)」では、球体、三角錐、立方体、という身体とは異なる立体の服を発表
ファッションデザインとの出会い
―― 森永さんがファッションデザインを始めたきっかけを聞かせていただけませんか。
僕とファッションの出会いは唐突でした。全くファッションのない場所で服と遭遇したんです。
大学受験のために通っていた予備校で、西谷昇二先生というカリスマ的な英語講師が、毎回授業の合間に10分くらい余談を話してくれました。映画とか、音楽や文学の話を。受験勉強に追われる日常とは違う、非日常。まだインターネットが普及していなかったので、その10分間を逃がすまいと、僕は教室の最前列に陣取りテープレコーダーで録音していました。
その先生が、ある日ファッションの話をしたんです。予備校の卒業生で、早稲田大学に通いながら自身のブランドを立ち上げた神田恵介さんというデザイナーの話でした。当時、僕にとってファッションは遠い存在でした。でも先生が一着の服を見せて、神田さんが自己表現の手段として服をつくっていて、服の一着一着には曲のタイトルのように名前を付けていると話してくれました。伝えたいことをタイトルにして服に縫い込んでいる、曲にメロディーと歌詞があってメッセージが伝わるように、服も色、かたち、テーマがあってメッセージを伝えられる、と。
僕は、服には伝える力がある、そして、服は言葉を持つ、そんなことを考えたことはかつて一度もなかったので、とにかく感動してしまったんです。
授業が終わると、僕は話の続きを聞きたくて講師室に駆けつけました。いつもは部屋の前に長蛇の列ができているのに、ファッションの話がほかの生徒には刺さらなかったのか、僕一人でした。教室では、みんなと同じ受験勉強のゴールを目指していたはずなのに、講師室には僕一人だけ。とても孤独感を覚えました。ただ、周りがいないことが逆に、その日誇らしく、輝いて見えたのです。
それまで僕はバスケやピアノ、少林寺拳法など「型」があるものをやってきました。既存の型に合わせることで評価をされ、そこから外れることはNGだった。でもファッションはそうではないところに正解があるのかもしれない。数が少なければ少ないほど輝く世界。周りのみんなと違うこと、みんなが気づかないことに気づくこと、一人でそれを信じること。先生の話を聞いて僕はすっかり嬉しくなって、もっとファッションのことを知りたい、神田恵介さんの弟子になりたいと思って同じ大学の同じ学科を目指すことにしたんです。
晴れて同じ大学の同じ学科に合格、入学しましたが、まだみんながスマートフォンを持っていない時代だから、学内中を回りながら、いろんな人に「神田恵介さんを知りませんか」と尋ねて歩き、念願の弟子入りを果たしました。その後、神田さんが開催したファッションショー見る機会がありました。なんとファッションショーの会場は、走る電車の中。インビテーションは切符でした。7月4日の午後9時24分、の電車に乗ってください、という指示がありました。明らかにファッション好きと思われる若者が数百人と集まり、その電車をほぼジャックするような形で僕らを乗せた電車が出発しました。神田さんの服を着た一人のモデルが人をかき分けて歩き始めると、車両の通路は一瞬にしてファッションショーのランウェイに変わりました。
生まれて初めてのファッションショーはあまりにも衝撃でした。というのも僕はこの路線で通学していて、毎日何気なく見ていた日常の景色が、服を通じて全く違うものに変容してしまったわけです。わずか20分ほどのショーでしたが、見ているうちにドキドキして涙が流れてきました。服ってすごい。そんな感情は初めてで、僕のいる日常はもう日常ではなくなっていました。服は日常を変え、服は人を変える。その服の力を信じようと思いました。それまでは、服づくりをしようと考えたこともなく、ただファッションが好きなだけでしたが、日常から非日常へと世界を変えるスイッチが入ったその日のその日、服をつくることを誓いました。服を通じて日常を変えてみたい、と強烈に思った。それが始まりです。
―― 20年以上にわたってアンリアレイジの活動を続けてこられました。設立当時から変わらないこと、逆に変わったことはありますか。
変わらないものは、ブランド名が示す通り「日常と非日常」、そしてその間にある境界線をずっと追求しています。テーマは、時によって身体であったり、知覚や光学的なことだったりと変わっていきます。時代とファッションは密接に関わっているので、それまでファッションの正義や常識とされていたものが次の瞬間に非日常に振れてしまうこともあるし、その逆もあります。
例えば100年前、シャネルは、女性がコルセットを付けてウエストを細くしていた時代に、身体が自由に動くジャージーのスーツを作りました。当時は非日常だったスーツは、今では日常ですよね。コルセットの方が非日常に変わった。このようにファッションは時と共に変わっていくものなので、絶対的な答えを探そうとするよりは、今はどっちに振れているか、寄っているかということをよく見ようとしています。
―― 2013年秋冬コレクション「COLOR」でフォトクロミック材料を採用し、25年春夏「WIND」は空調服。25年秋冬「SCREEN」は液晶画面の服で世界を驚かせました。素材やテクノロジーの取り入れ方など、プロダクトデザインに通じるところがあるように思います。
ファッションの世界では「ここまでがファッション」といった暗黙の境界線があって、どこか閉鎖的かもしれません。でも僕はそのカテゴリーをもう少し拡張できると考えているんです。
フォトクロミックは光が当たると色が変わる材料です。これを使ったら色が変わる服ができるかもしれないし、柔らかい液晶をまとうことができたらファッションの可能性が広がりますよね。テクノロジーやデジタルはファッションと混ざりにくいと思われているところがあります。でも考えてみれば、さまざまな技術や素材を組み合わせて糸や布ができますし、ミシンがなければ服も出来上がりません。テクノロジーと服は密接に結びついている。両者がしっかり混ざった時にはファッションを大きく進歩させることができるのではないかと信じているので、積極的に取り組んでいます。

2013年秋冬コレクション「COLOR」では、紫外線などの光に反応すると分子構造が変化し、白からさまざまな色に変わる服を発表
―― 一方で、手で大切に作っていくこと、人間の手からしか生まれないものについても、常に立ち返って大事にされています。
例えば「SCREEN」(2025-26年秋冬)は、人間の手とはかけ離れた世界に見えるかもしれませんが、実は小さなLEDを何万粒も、ひとつひとつ手作業で縫い付けています。まるでオートクチュールのようです。ものごとの対極にある強度が必要で、その間を行き来することができないと、アンリアレイジらしい服にはならないんです。

最新コレクション「SCREEN」(2025-26秋冬)では、黒い服が液晶スクリーンとなり、あらゆる色やパターンを映し出し、服がメディアとして進化した
コクヨデザインアワードへの期待
―― そんな森永さんが、コクヨデザインアワードの審査に参加する理由を教えてください。
コクヨデザインアワードは受賞作を製品化して、人の手に渡るところまでサポートしているアワードです。そうした、まだ形にはなっていないけれど、やがて日常になる可能性があるもの。僕自身がこれまで「日常と非日常」の境界を探ってきた経験から、今までなかったものを拾い上げられるといいな、と思いました。
個人的にはプロダクトとファッションは真逆にあるものと思っています。ファッションはプロダクト以上にすごい速さで移り変わっていくものなので。でもファッションの視点やファッション自体がプロダクトの分野に入っていくきっかけになるといいな、とも考えています。
―― ファッションにとってもプロダクトデザインから学ぶことがありそう、ということでしょうか。
ファッションの世界では、いわゆる「センス」が大事にされています。一方、感覚だけで服をつくっているわけではなく、そこに「ロジック」があることを僕は大事にしています。加えて、まだ世にない新しい考え方やコンセプトが形になっていくような「イノベーション」も絶対に必要。コクヨデザインアワードというのは、それらの接点があるような気がしていて、そこにも期待しているんです。
―― コクヨデザインアワード2026のテーマは「波紋」です。このテーマについてはどのように考えていますか。
僕は「神は細部に宿る」という言葉を信念として、ものづくりを続けています。「細部」というのは例えば、まわりの人が気づいていないこと、みんなが通り過ぎていくもの。その価値に気づいて、信じて、形として生み出せたら、大きな変革をもたらすことがあります。服で言えば、1個のボタンや1本の糸が服全体の印象を変えるし、できあがった1着が1人に届くことで、その時代や社会を変えていく。実際にファッションの世界ではそういうことがたくさんあるんです。
テーマの「波紋」については、その起点にあるものはとても小さく、数も少ないかもしれません。けれどその小さな一滴が全体に影響を及ぼして、時代や社会、日常を変えていくスイッチになるかもしれない。僕自身がものづくりを通してそういうものを求めてきたし、アワードの審査を通してそういうものを見られたらいいですね。

―― 大海から一滴を見いだすのは、審査員として大変なところがあるかもしれませんね。
その一滴がどこかに落ちないと波紋は生まれないので、必ずどこかに跳ね返ったり、何かに影響を及ぼしている。それを想像できるものが大事なのかもしれません。どのような使われ方をして、どんな日常を変える余地を持っているか、そうした広がりを感じさせるものを見つけたいですね。
―― 海外でも活躍されている森永さんから、国際的なデザインコンペとしてコクヨデザインアワードに期待することはありますか。
世界には実に多様な価値観がある中で、まだその人にしか見えていない世界や、その人の内側から生まれたものが、結局のところ世界を突き抜けていくのではないでしょうか。グローバルなコンペティションだからこそ、グローバルではない個の視点もとても大切になるのでは。ファッションの世界では、グローバルなトレンドに抗う、杭を打とうとする人たちもいて、そうした新しい価値観を模索する姿勢が大事だと思います。

―― 言い換えると「反骨」みたいなことでしょうか。
反骨や反抗というよりは、グローバルの目線を踏まえた上で、自分の立ち位置を明示するという、ものづくりのあり方です。そのためには今の時代や流れを認識していなければいけません。
僕はファッションデザインの若手を審査したり、助言をする機会が多いのですが、いつも「ふたつの世界を大事にしてほしい」と言っています。ひとつは、自分の外にある世界。社会情勢、戦争や環境問題を含めて、今の世界で何が起きているのか、ということ。もうひとつは、自分の中にある世界です。自分の中の世界で闘い、その世界を信じて、それを外の世界に打ち出していけるデザイナーが増えるといいな、と思っています。
―― これからコクヨデザインアワードに応募する方々に、ヒントになるようなアドバイスや心構えがあったら教えてください。
波紋は一滴から始まります。どんなに小さくても、数として少なくても、なんとかその一滴を絞り出して、どこかに垂らしてみてほしい。今の時代、どれだけシェアされるか、フォローされるか、バズるかが重視されがちですが、そうした大きなところに向けて作ろうとするのではなく、誰か一人にしっかり伝わればいい。そういう考え方やあり方が見直される時ではないでしょうか。僕も審査員として、今はマイノリティかもしれないその一滴をなんとか見つけて審査をしたい。そういうものこそ、大きな何かを生み出し、たくさんの人の心に届き、社会を変える可能性があるはずなので。楽しみにしています。
―― ありがとうございました。