Vol.32 CASE
「もっと気軽にコミュニケーション!」をカタチにした、オフィスのたまり場<hangout(ハングアウト)>
掲載日 2025.11.17

Interviewee
-
高木 梨帆(たかぎりほ)
グローバルワークプレイス事業本部 ものづくり開発本部 サーフェイス開発部
-
靍﨑 健太郎(つるさきけんたろう)
グローバルワークプレイス事業本部 ものづくり開発本部 インテリア開発部
-
宮原 秀彦(みやはらひでひこ)
コクヨKハート(開発当時)
-
大塚 茉鈴(おおつかまりん)
グローバルワークプレイス事業本部 ものづくり開発本部 シーティング開発部
-
後藤 由芽(ごとうゆめ)
グローバルワークプレイス事業本部 ものづくり開発本部 デザインセンター
-
小林 優季(こばやしゆき)
グローバルワークプレイス事業本部 ものづくり開発本部 ものづくり戦略本部 商品戦略部
今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト
今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト
<hangout(ハングアウト)>
「オフィスでカジュアルにコミュニケーションができる場所をつくる」というコンセプトから開発が始まった<hangout>。「どんなデザインにするか」「安全性とカジュアル感を両立するには?」などさまざまな課題に一つずつ向き合いながら、まったく新しいオフィス家具を創り上げた6人の開発メンバーに、企画の意図から開発プロセスで感じた苦労、それぞれのパーツに込めた思いなどを伺いました。
多くの人が持つ本質的なニーズを
ワークショップで掘り起こした
まずは、<hangout>の開発がスタートしたきっかけをお教えください。
高木:コクヨのインクルーシブデザイン「HOWS DESIGN」ではこれまで、具体的に何を創るか決めたうえでの製品開発が主流でした。しかし<hangout>は、どんな製品を創るかも実は決まっていなかったのです。開発スタートのきっかけとなったのは、「コミュニケーションをセンシティブにデザインする」というテーマで行ったワークショップでした。

開発のプロセスを語る高木さん
そもそもコミュニケーションをテーマにしたワークショップを実施したのはなぜですか?
靍﨑:多くの企業・組織にとって「オフィスでコミュニケーションをどう活性化するか」は常に課題となっています。インクルーシブデザインというと、製品そのもののユーザビリテイやUI(ユーザーインターフェイス)など、より具体的な内容に目がいきがちですが、コミュニケーションという概念的なものと組み合わせることで、新しい切り口の気づきが得られるのではないか、という期待がありました。
実際にワークショップで宮原さんたちリードユーザーの方々と議論したところ、予想外の気づきが得られたのです。
宮原:私は常日頃、「オフィスでもっといろいろな人とコミュニケーションをとりたい」と感じていました。私は50代で障がい者になりましたが、それまではオフィス設計を手掛け、いろいろな場所へ出かけてきました。ですから、これまでの経験を若い世代のワーカーに伝えたい思いが強かったのです。
しかし私から見ると、テーブルやチェアーが並んでいるコミュニティスペースは「わざわざ集まる」という印象が強く、気軽にコミュニケーションできる雰囲気ではないように感じられました。そこで、「もっとフランクにコミュニケーションができる場所がオフィスにほしい」と提案しました。

第1回ワークショップの様子
小林:私たちは当初、「コミュニケーションを促す場」といっても「リードユーザーの方が使いやすいよう、安定した手すりをつけなければ」といったインクルーシブデザインの視点ばかりで考えがちでした。でも宮原さんの思いを聞いて、「誰かと話したい、つながりたい」という気持ちは誰もが持っていることに気づき、ワーカーにとっての本質的なニーズが見えてきました。
この気づきをもとに「オフィスの中でワーカーが気軽に集まれる場所をつくろう」という方向性をメンバーで固めることができたときは、とてもうれしかったですね。
「カジュアル」と「安全」を
両立するカタチを試行錯誤
「気軽に集まれる場所」という抽象的なコンセプトを製品に落とし込むのは難しそうですが、どんなふうに具体的な形を決めていったのでしょうか?
高木:宮原さんの意見も踏まえながら、「人が集まるのってどんな場所だろう?」と考え、各々普段の生活の中で観察したり、写真を集めたりしていました。そのなかで、そういえば学生が手すりにたむろしてるシーンあるよね、自分もやったことある、という話になり、本社外のスロープの手すりの前にソファを置いて実験してみたりしました。
宮原:「集まりやすさ」にはいろいろな要素がありますが、私は右半身に麻痺があるので、「とっさに体をあずけられる場所がある」といった安心感も重要だと考えています。
靍﨑:手すりは、ややもすると「高齢者やハンディキャップをかかえている人が使うもの」という先入観を持ってしまいますが、実は健常者も無意識に使っているし、色々な使い方をしている。それをよりポジティブに、堂々と表現してあげると面白いんじゃないかと考えました。
高木:宮原さんから得た最大のインサイトは、障害がある=動かなくて済むように配慮する方がよいという思い込みがあったが、実はリハビリもかねて体を動かしたいと思ってらっしゃったこと。そこから、安心してつかめる、もたれられる、という要素が出てきた。動きたいけど転ばないよう気を付けたり、体に負担がかかる状態ではコミュニケーションに集中できない。そこをさりげなくサポートすることで宮原さん含め誰もが安心してコミュニケーションに没入できる場になる、というのがhangoutの根幹です。
その後、開発メンバーで話し合ううちに「ストリート感覚」と「インクルーシブデザイン」が結びつき、「ストリートでのラフなコミュニケーションをオフィスでも実現させる、カジュアルで安全な製品」という方向性を固めることができました。ちなみに、<hangout>は英語で「たまり場」のようなニュアンスです。

実際にシーンをイメージしながら試作品の改良を重ねた
開発を進める中で、「カジュアルなデザイン」と「安全性」を両立させるためのご苦労がたくさんあったと思いますが、いかがですか?
高木:大前提として家具が転倒するのは避けなければならないので、ポールの脚にそれぞれ15キロのおもりをつけることにしました。素材を何にするかもメンバーみんなでディスカッションし、鉄の鋳物でつくることにしたのですが、「どう小さく収めながら15kg確保するか」「どう成形するか」は悩みどころでした。
宮原:試作段階ではおもりが大きく、足が引っかかってつまずきそうで怖かったので、「できるだけ小さい形にしてほしい」とお願いしました。重さとサイズ感の調整は苦労したポイントの一つです。

試作品を実際に試しながら、リードユーザーの立場から要望を出していった宮原さん
後藤:色も工夫のしどころでしたね。色覚に特性のある人が認識しやすいカラーにしたくて、オフィスらしい黒やホワイトブラウンのほかに、「フロアに置いたときに識別しやすいテラコッタとイエローもラインアップに加えよう」と話し合って決めました。
ただ、きつすぎる色合いだとオフィスの雰囲気になじみにくいので、塗料の色見本をメンバー数人で見て「見えやすく、しかも強すぎない」色合いを検討しましたね。
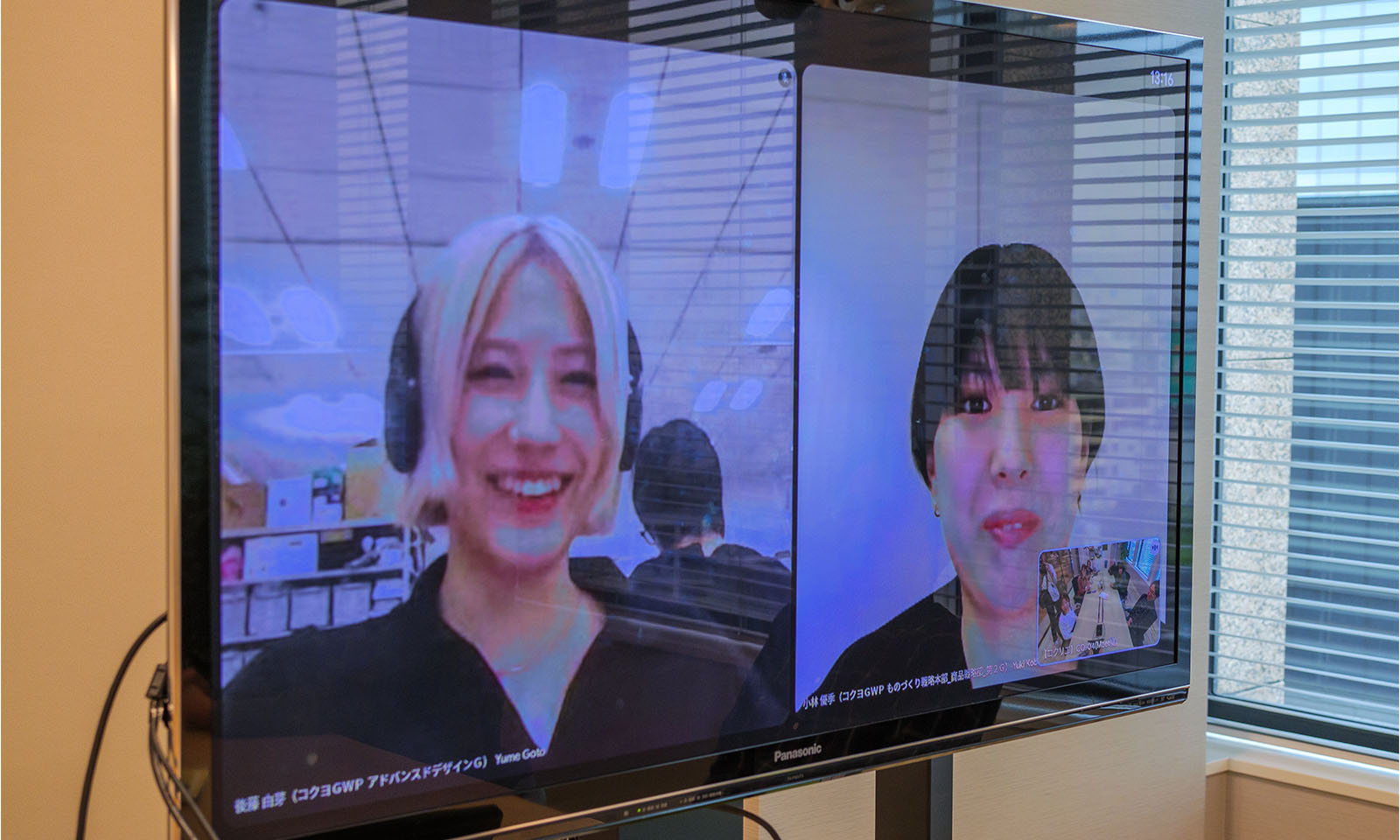
品川オフィスからオンラインで取材に参加した後藤さんと小林さん
今までにない製品だからこそ
生みの苦しみは大きかった
ゼロから創り上げる、という点でも、さまざまなトライ&エラーがあったのではないでしょうか?
大塚:<hangout>は椅子やテーブルなどいろいろな要素が組み合わせられた製品なので、試作品を検証するにしても明確な基準がなく、「どこをどうチェックしたらいいか」で悩みました。
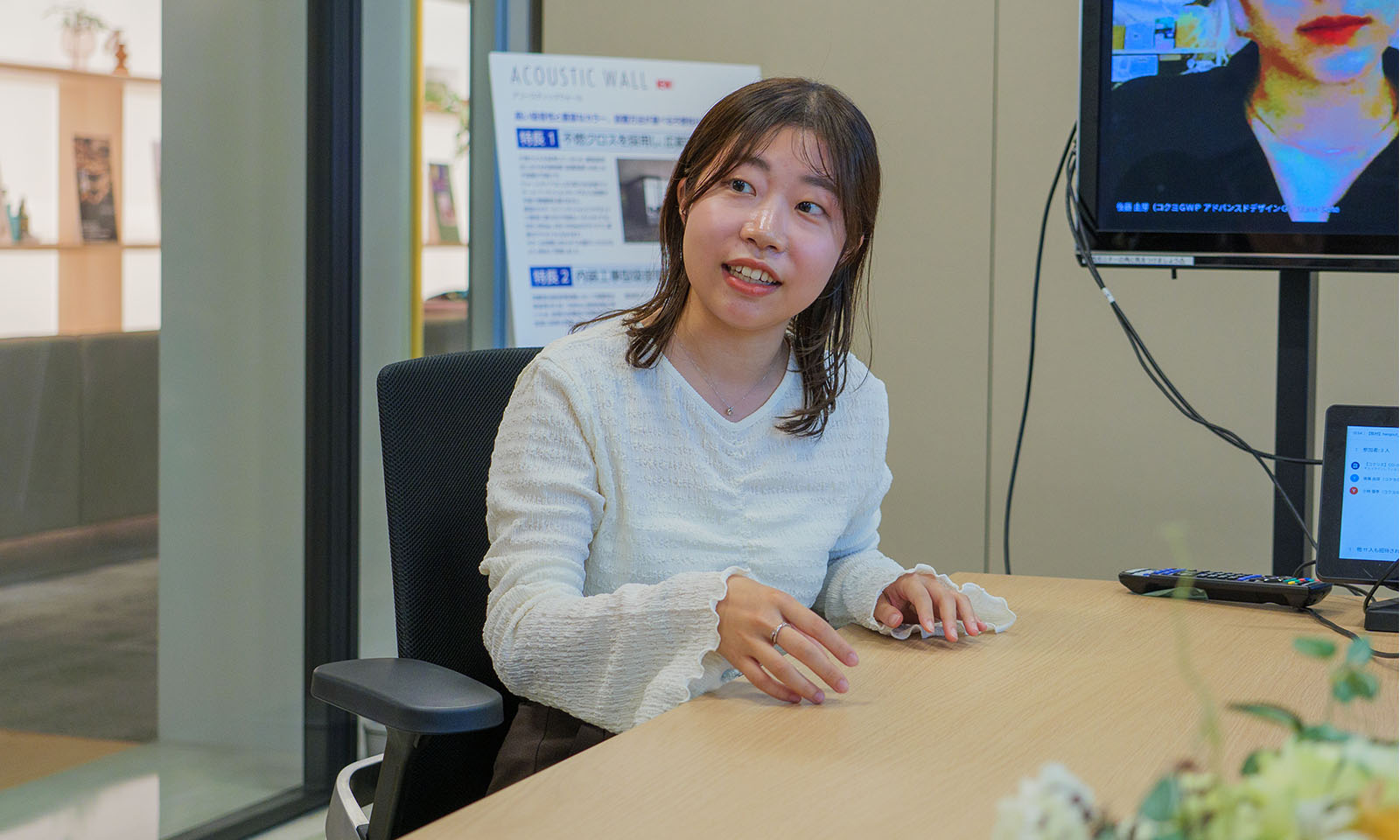
「まったく新しい製品なので、品質試験の基準もなく苦労した」と大塚さん
靍﨑:腰かけられるポールの高さも悩みポイントですね。初めは750mmに設定していたのですが、大塚さんに試してもらったら「足がつきません」と指摘されましたよね。

「デザイン性と安全性の両立に苦労した」という鶴崎さん
高木:逆に低いと、背の高い開発メンバーが座ったときに心地よさを感じられないので、最終的に720mmというベストな高さを見つけるまでには試行錯誤を繰り返しました。
ほかにも、「テーブルをどの位置に配置すればどんなコミュニケーションが生まれるかか」「L型のフレームはどのくらいの長さにすると空間の中で収まりがよいか」など、考えどころがたくさんありましたね。
多様なコミュニケーションが
生まれるきっかけになってほしい
<hangout>は2025年12月に発売予定ですが、かなり前から試作品をつくり、少しずつ改良を加えていったそうですね。実際に利用した方の声やアクションを開発に生かした部分もあるのでしょうか?
靍﨑:検証として、自社のオフィス内や工場など、色々な場所に設置してみて、様々なシチュエーションでの実ユーザーの声を集めました。さきほど出たフレームの高さもそうですし、ソファの座面高さや硬さ、視線の方向など、過ごし方の部分もブラッシュアップしていきましたね。
宮原:リードユーザーという立場からこのプロジェクトに参加しましたが、以前の業務で得た視点から「オフィス空間にどんな家具がなじむか」という観点からも積極的に発言しました。遠慮なく意見を言って、受け止めてもらいながらモノづくりをしていくプロセスはとても楽しかったです。
小林:品川のショールームにも試作品が設置してあるのですが、スーツ姿のお客さまがはしゃぎながらもたれたり腰掛けたりしているのを見て、「<hangout>をきっかけに、いろいろな世代の人がオフィスでくつろいだ表情を見せてくれるかもしれないな」とhangoutのポテンシャルを感じました。
実際、これから全国のさまざまなオフィスに<hangout>が置かれることになりますね。どんなふうに活用してもらいたいですか?
高木:若いワーカーが、<hangout>の設置場所に集まって悪だくみしている姿を思い浮かべるとワクワクします。そこで出た話題がきっかけになってイノベーションにつながったら最高ですね。
宮原:オフィスだけでなく、いろいろな公共空間に置いてあると、さらに多様なコミュニケーションが生まれるのではないかと期待してしまいます。
大塚:<hangout>のある空間でそれまでとは違ったコミュニケーションが始まって、そこで生まれた価値観が企業に浸透していくといいな、と思っています。

左から、高木さん、靍﨑さん、宮原さん、大塚さん、後藤さん、小林さん
取材日:2025.10.22
執筆:横堀夏代
撮影:松井聡志
編集:HOWS DESIGN チーム




