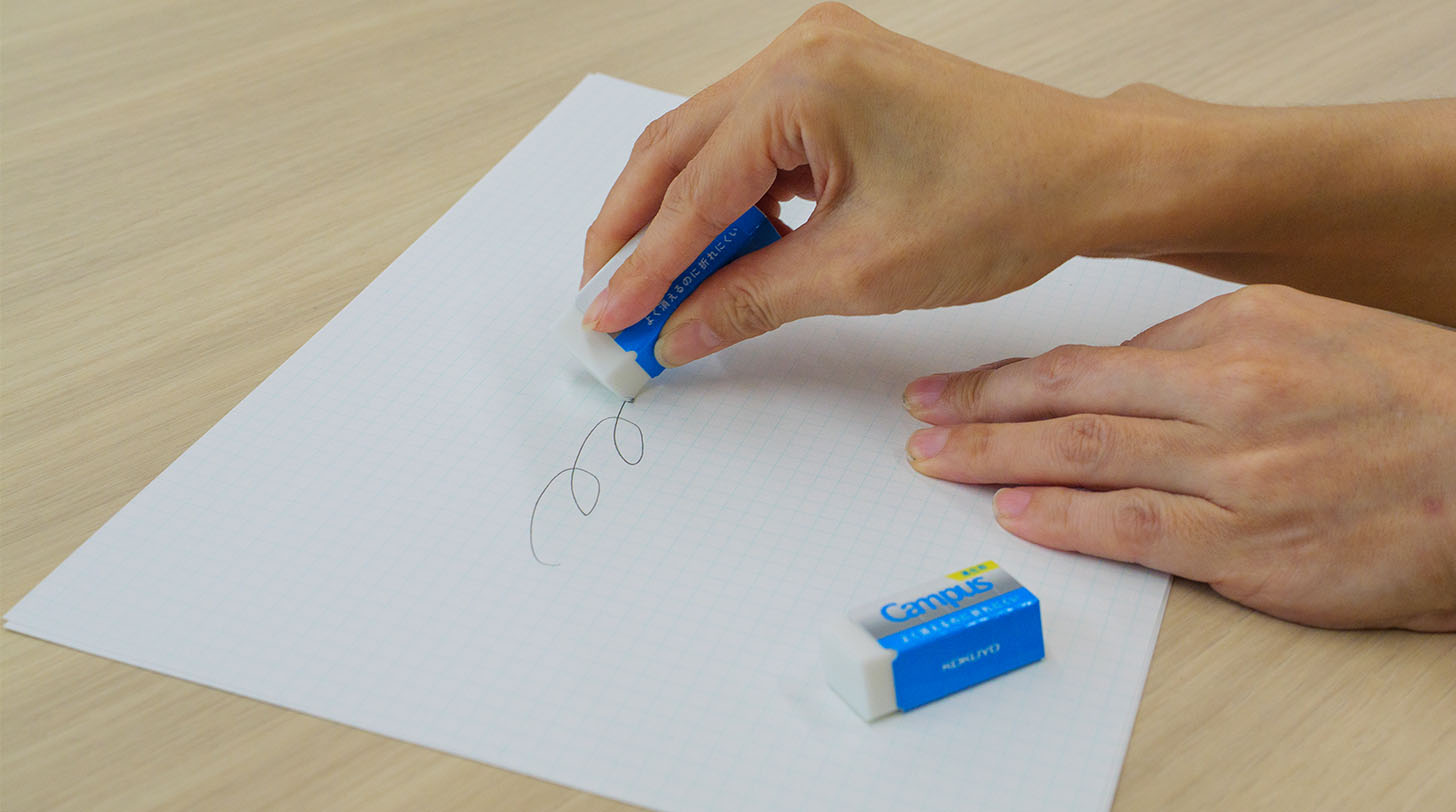Vol.31 CASE
自分の席が見つかる「FORSE」は、過ごし方の違いから生まれた新発想のロビーチェアー
掲載日 2025.11.17

Interviewee
-
安江 篤史(やすえあつし)
グローバルワークプレイス事業本部TCM本部マーケティング部
-
靍﨑 健太郎(つるさきけんたろう)
グローバルワークプレイス事業本部ものづくり開発本部インテリア開発部
-
谷川原 結衣(たにがわらゆい)
グローバルワークプレイス事業本部ものづくり開発本部インテリア開発部
-
昌島 成好(まさじましげよし)
コクヨKハート
今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト
今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト
FORSE(フォルセ)
「隣の人との適度な距離感を保ち、座る際の心理的な負担が少ない」「様々な立ち上がり姿勢に自然と寄り添うひじ掛け」「テリトリーを確保して長時間でも快適に待てる」など、多様な人が自分に合う席を見つけやすい新しいロビーチェアー。着座率の向上はもちろん、座る人の緊張を和らげるソファのようなボリューム感を感じさせるデザインでストレスの軽減も期待できる。脚の色や、張地の色を豊富に選ぶことができ、CMFによって様々なデザインテイストの空間にマッチすることができる。
どこに座る? なぜ選ぶ? ワークショップを通して見えてきた、待合室での過ごし方の多様性
まずは製品開発に至った経緯と、具体的にどのように開発を進めてきたのかをお聞かせください。
安江:コクヨとしては約10年ぶりとなる病院向けロビーチェアーの企画が立ち上がり、どういった着眼点で開発を進めるかを検討した結果、会社を挙げて取り組んでいるインクルーシブデザインを組み込んでみようとなったのが始まりです。HOWS DESIGNのプロセスに沿って開催した第1回のワークショップでは、昌島さんをはじめ、たくさんのリードユーザーにご協力いただき、病院の待合室での行動や困りごとについて気付きを得るための検証を行いました。

企画を担当した安江さん
靍﨑:当日は既存のロビーチェアーを並べて病院の待合ロビーをイメージした空間で、リードユーザーの皆さんに病院での過ごし方を再現していただきました。リードユーザーは、下肢障がいをお持ちの方や車椅子を使用する方、年配の方などさまざまです。
昌島:病院の待合ロビーにいると仮定して、まずどこに座って待つか?と考えた時、僕の場合はチェアーの端に座りがちですが、リードユーザーの中には、真ん中で腰を深くかけて座りたいという人もいましたよね。

リードユーザーの昌島さん
安江:でもやっぱり、昌島さんのように端に座られる方がほとんど。どこに座るかという観点でいえば、ロビーの前方のチェアーに人が集まりがちなこともワークショップでの気付きの一つでしたね。病院は基本的に体調が優れない人が行く場所なので、なるべくカウンターの近くに座って「呼ばれたらすぐに動きたい」「早く用事を済ませて帰りたい」という心理が働くようです。
靍﨑:製品のデザインという視点だけで考えると、シートの硬さや柔らかさ、肘掛けの使いやすさなどに目が行きがちですが、実際にワークショップで得た一番の気付きは「ユーザーの状況によって快適な過ごし方が全く違う」という点でした。製品単体のミクロな視点ではなく、過ごし方や空間単位でのマクロな視点で捉えることが開発を進める上での大きな指針になりましたね。
安江:どの席でも価値が同じなら、自分にとって都合のいい位置で選ぶしかないので、結局は仕方なく選んでいる状況です。そういった結果を踏まえて、各々がもっと自分の過ごし方に合った席をポジティブに選べるロビーチェアーがあるといいよね、と。
一方で、病院側が理想とするロビーチェアーはどういったものなのでしょうか。
安江:大きく二つあります。まず、経営者が重視するのは、病院のイメージアップを図るためのデザイン性や座り心地のよさです。一方で、現場のスタッフが求めるのは、清掃のしやすさや座ってゆっくりと待ってもらえるもの。着座率を上げることで、動線の確保や待ち時間による患者さんのストレス軽減につなげることを期待されています。
谷川原:特に着座率については、病院側だけでなく、「奥まった真ん中の席には座りにくいけど、本当は座りたい」というユーザーニーズとも共通している部分なので、ロビーチェアーの課題としてよく取り上げられますよね。

開発チームの靍﨑さん
安江:端の席を好む人が多いと真ん中は避けられがちで、かつ、隣に人がいると座りにくいと感じる人も少なくありません。そうすると、立ったまま待つ人が増え、混雑した病院の中ではぶつかったりケガをしたりする危険性も出てきますよね。ワークショップでもそういった意見が出てきたので、着座率の課題を解決することもコンセプトの一つとなりました。
靍﨑:それに対して出た案の一つが、真ん中の座席を広くするというもの。解決策としてはそれだけでも十分かもしれませんが、ユーザーの行動を観察していると、人によって過ごし方に対するニーズは様々であることが分かってきました。それなら、ゆったりとした肘掛けが付いたタイプや仕切りがあるタイプなど、もっといろんな過ごし方に寄り添うバリエーションが必要なんじゃないかという話になり、アイディアがさらに広がっていきました。

肘掛けの持ち方も人それぞれ。立ち座りの際に「握る」「面で押す」「前淵を掴む」という3つのパターンが見られた
安江:それらをもとに、座席にさまざまな差異をつけて再度検証を行ったのが2回目のワークショップ。すると、1回目よりも着座傾向にばらつきが見られたので、コンセプトの方向性が間違っていないことを確信し、企画会議を通して本格的な製品化へと動き出しました。
“ソファらしさ”を軸に、かつてないバリエーションを展開。「座らされている」から「座りたくなる」ロビーチェアーへ
開発が進む中で、どんな苦労がありましたか?
谷川原:デザインに落とし込むフェーズでは、いろいろな方向性の案が出たのですごく悩みましたね。人に対する優しさを重視したものと、空間への馴染みやすさも兼ね備えたもの、どちらを取るべきか……と。
靍﨑:最初は4パターンの候補を出して、デザインの精度を高めながら絞っていったのですが、大きく分けると「ロビーチェアーらしいもの」と「ソファらしいもの」がありました。
谷川原:ロビーチェアーらしいといえば、同じ形の席がずらっと連なっているイメージですね。
あと、シートが硬い。張地ではなく、ほとんどがビニールレザーで、どうしてもチープな印象になりがちです。
安江:多様な過ごし方という今回のコンセプトにマッチするものを考えた結果、座り心地や人に対する優しさを重視したソファらしいデザインが採用されることになったんですよね。
谷川原:人の体形に沿わせて座り心地を良くしたロビーチェアーはあるものの、ソファのようなふわっとした形のロビーチェアーはおそらく今までにないと思います。

開発チームの谷川原さん
靍﨑:まっすぐ前を向いて座るのがロビーチェアーだとすると、体を少し斜めに向けて座ったり、姿勢をくずしてみたりと自由な体制をとりやすいのがソファ。この座り方の自由度の高さを実現できたのが、ソファらしいデザインに振ったメリットの一つです。
谷川原:FORSEは、ソファらしさを起点に、今までにないほど多彩なバリエーションを展開しています。従来の「座らされている」という感覚ではなく、自ら選んで「座りたい」と思える席がきっと見つかるはずです。
靍﨑:象徴的なのは、中央の座幅が広いセンターワイドシートと、過去製品から継承してきたサイドラウンドシートの組み合わせ。中央席はリッチな席になっており、左右の席は立ちあがりやすさはもちろん、ベビーカーや車いすの人とともに過ごしやすくなっています。
安江:他にも、しんどくてよりかかりたい人にはハイバックタイプ、すぐに動きたい人にはベンチタイプなど、いろいろな機能を持っていながら、デザインが統一されていることも特徴ですよね。同じデザインのチェアーを設置することでロビー全体に統一感が生まれ、病院の経営者視点のニーズも満たすことができます。
昌島:僕はまだ完成品を見ていないのですが、皆さんの話を聞いていると仕上がりが俄然楽しみになってきました!(編集部注:下記の写真撮影前にインタビューしています。)

肘掛けの最適な形状についても検証を重ねた
アイディアは自然体の行動から生まれる。リードユーザーがHOWS DESIGNプロセスに参加する意義
HOWS DESIGNのプロセスに沿った開発を振り返って、改めていかがでしたか?
昌島:僕たちの何気ない一言がどんどん具現化されていくのは、成長の過程を見ているようで本当にワクワクしました。最初は「何か役に立つことを言わなあかんのかな?」と身構えていましたが、普段の自分をそのまま再現したり、思っていることを率直に伝えたりすることで開発が進んでいったので、自然体でいることが一番なんだなと思いましたね。
靍﨑:開発側としても、リードユーザーの行動については、まずは観察に徹することが大事だと気付かされました。こちらがあれこれ口を出してしまうと、先入観を与えてしまって昌島さんたちの素直な行動が見られなくなってしまうので。基本的にはじっと見守って、何か面白い気付きがあったときに対話をしながらヒントを探っていくのが理想なのかな、と。
昌島:確かに、先入観があると自分が普段やらないような行動をしてしまいそうですが、それだと意味がないですもんね。開発が進む中でも「これは違うんじゃない?」と思ったら、僕ははっきり伝えますよ。
谷川原:昌島さんはスパッと言ってくれるので、開発チームとしてもすごく助かっているんですよ。

ワークショップの様子
安江:今回は、コンセプトや方向性を最初に決めず、まっさらな状態でワークショップからスタートしたのがよかったのかなと思っています。昌島さんがおっしゃったように、自然体で参加してくれたからこそ、FORSEにつながるアイディアが生まれました。リードユーザーと一緒に作り上げるHOWS DESIGNのプロセスを経たからこそ得られた成果だと思っています。
谷川原:本格的にHOWS DESIGNプロセスに関わったのは初めてでしたが、すごくいい取り組みだと感じました。最初は、リードユーザーの皆さんから気付きを得ることばかりを考えていましたが、自分も同じような考え方をすることに気付かされ、様々なハンディをかかえる人たちや高齢者だけでなく、もっと幅広い人に受け入れられる製品にできるんだということに気付きました。このプロセスを踏めば、これまで気付かなかった本質的な価値を見つけることができるのではと思えましたね。
靍﨑:どうしても僕たちは仮説を持ってしまうんですよね。観察をする前から「きっとこうだろう」というバイアスがかかっている部分もある。チームで対話しながらデザインをしていくという経験は、自分にとっても発見が多くありました。リードユーザーやチームメンバーととことん意見を出し合ったからこそ、ユーザーの共感を呼ぶことができたのかなと。HOWS DESIGNプロセスは、価値を研ぎ澄ませるための近道になっている気がしますね。
今回は病院向けのロビーチェアーという企画でしたが、人が待つ場所というのは病院だけに限りません。銀行や空港などさまざまな公共空間で、多様な人に寄り添うロビーチェアーとして広がっていってほしいと願っています。

前列左より安江さん、昌島さん、谷川原さん。後列左より靍﨑さん。インタビューには参加していませんが開発メンバーの菅原 菜月さん、寺尾 保紀さん、橋爪 汐音さん。
取材日:2025.9.24
執筆:秋田志穂
撮影:松井聡志
編集:HOWS DESIGN チーム