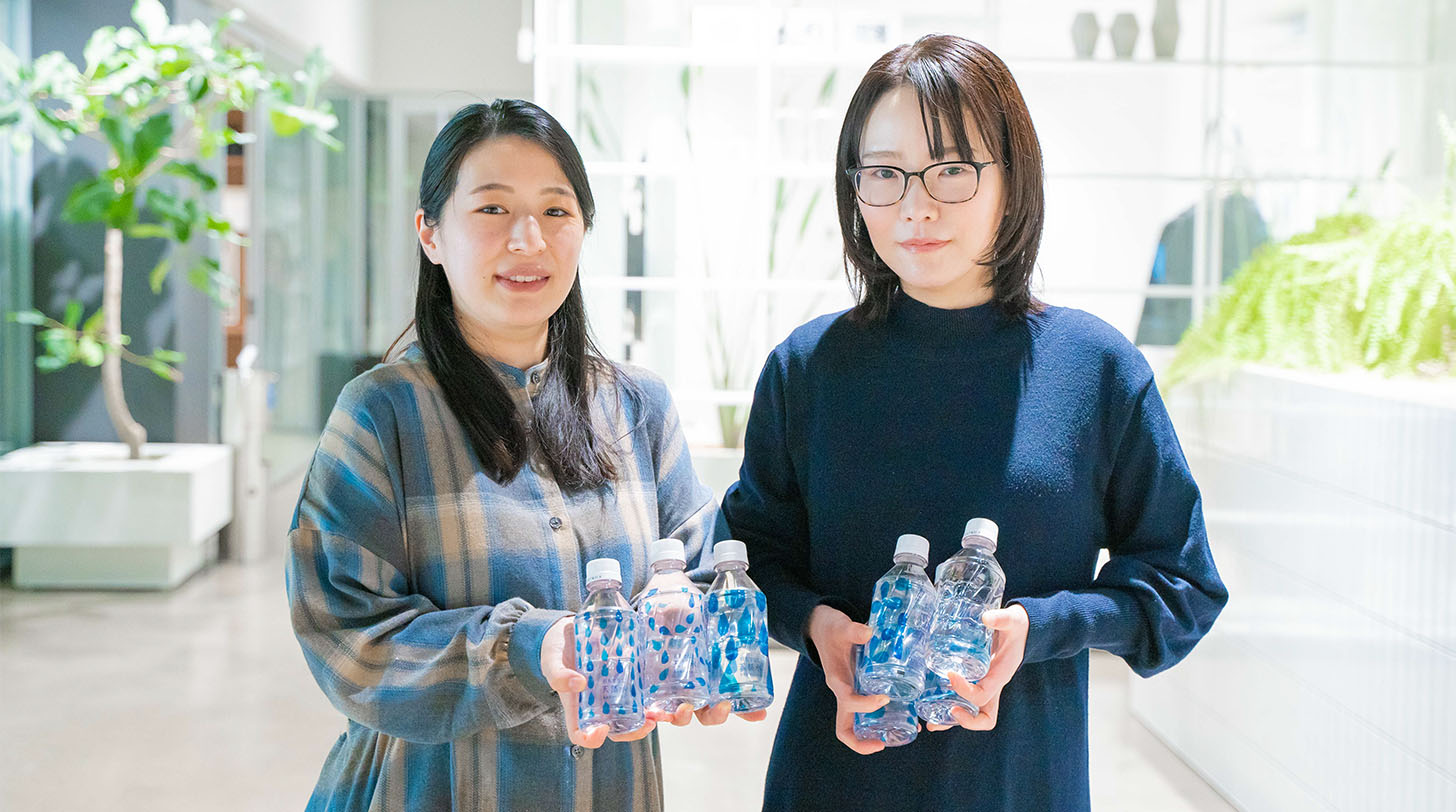Vol.27 CASE
“持たされる”から“持ちたい”デザインへ。わかりやすさにこだわったGPSトーク端末「はろここトーク」
掲載日 2025.07.04

子どもたちが「仕方なく持つ」のではなく、「自分から持ちたくなる」GPS端末を目指して、防犯や見守りだけにとどまらず子どものチャレンジを応援できる商品としてリリースされたGPSトーク端末「はろここトーク」。障がい福祉の現場の声や当事者の視点を丁寧に取り入れながら実現した製品の、開発プロセスについて聞きました。
Interviewee
-
横田 早紀(よこた さき)
コクヨ株式会社 イノベーションセンター IoT事業戦略ユニット ハローファミリーグループ
-
中筋 翔大(なかすじ しょうた)
株式会社シーアイ・パートナーズ ブロックマネージャー 兼 合同会社コスモ 職務執行者
今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト
今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト
コクヨのGPS 「はろここトーク」
「きく」「はなす」「しらせる」の3つの機能に対応したボタンを搭載、直感的で視覚的にもわかりやすいデザインのGPS端末。
製品紹介ページはこちら
持つ人を守るものから、持つ人の嬉しいを発信できるものに
今回の企画の経緯と、開発の進め方について教えてください
横田:2023年のサービス開始時に発売したHello! Family.シリーズ(以下ハロファミ)の初期ラインナップとなる子どもの見守り端末は4種類あるのですが、ブランドコンセプトである“双方向の見守り”と“家族の今をつなげる”という部分をもう少し強化できるのではないかと感じていました。既存製品には声を送れる機能がなく、今回の製品では、子どもからも発信ができるトーク機能をつけたいと考えていました。

横田:社内でデザインの方向性を何案か検討しつつ、前機種を実際に触ってもらった反応を見て方向性を調整したり、小学生たちのリアルな声を聞いたり、それらを反映させてはまた声を聞いて……といった繰り返しを重ねて開発を進めました。中筋さんにご協力をいただく中では実際に障がいのあるお子さんたちにGPSを持って通学や通所をしてもらったりと、色々な方法で声を聞き、反応を確かめながら開発することができたと思います。
実際に子どもたちの反応をみて気がついたことはありますか?
中筋:以前から、障がい福祉の現場からの意見やリアルな声を届けるという形で協力させていただいていたのですが、今回は弊社の事業所で障がいのあるお子さんやその親御さんにモニターをしていただきました。その中でまず感じたのは、「持ちたくなるデザイン」が非常に大事だということです。これまでの防犯ツールは「守る」ことが目的で、どちらかというとネガティブなイメージが強く、僕が学校教員をしていた時にも、多くの子どもたちは防犯ベルなどを親御さんに「持たされている」と感じていて、「仕方なく」身につけているという印象がありました。
横田:子どもたちにとってGPS端末は、親御さんに「何かあったら使いなさい」と言われて持たされているものなんです。でもそれが、おもちゃや携帯ほどじゃないけどちょっと楽しくて、子どもから「困ったとき」だけでなく、「うれしいとき」も発信できるものになったらいいなと思いました。
中筋:実際に弊社の子どもたちに使ってもらった中で「これはキーホルダーみたいでいい!」というポジティブな意見もいただいたので、デザイン次第ではそうしたネガティブなイメージを変えていける可能性があると感じました。

どのようなことに気をつけて意見を取り入れていったのでしょうか?
横田:はろここトークに限らず、新製品を開発するときに子どもたちにヒアリングをすると、私たちに気を遣って「良いね」と言ってくれるときもあります。なので、心から本当に良いと思ってくれているかを表情や様子を見ながら聞いていき、さらにそれを施設のスタッフさんの意見でも確認するということをしていきました。
中筋:デイサービスにしても子どもが自分から「行きたい」と言うことはあまりなくて、最初の一歩を踏み出すのはやっぱり親御さんなんですよね。ほとんどの子が、「こういうところあるよ」「行ってみたら?」という親御さんからの働きかけからデイサービスにつながってくれるんです。そうしたことも踏まえると、まず親御さんに「これいいな」と思ってもらうことがすごく大事だと考えていて、率直な意見や反応をいただくことを大切にしました。実際に、親御さんからの提案の仕方次第で子どもが前向きに「持ってみたい」「使ってみたい」と思えるかは変わってくると思うので、子どもにも自然とポジティブな気持ちが伝わっていくようにと願っています。

わかりやすいデザインは、日常生活のルールの中にある
製品特長とこだわった点について教えてください
横田:3つのボタンが直感的に操作できる仕様になっています。「きく」「はなす」「しらせる」といったそれぞれの機能に対応するボタンが用意されており、視覚的にもわかりやすいデザインです。そのため、子どもでも迷わずに「音声メッセージの再生」「音声メッセージの録音」「位置情報の送信」といった操作が簡単に行えます。
中筋:ボタンが1つしかなかった前機種について、親御さんからはボタンを押して位置を通知するだけでなく、子どもの声が聞けたりこちらから音声を送れたりすると嬉しいという意見がありました。
なぜかというと、通学時に障がいのあるお子さんにとっては、見知らぬ人に「どうしたらいいですか?」と尋ねるのが難しい場合があるからです。今回搭載したトーク機能があれば、親御さんや施設のスタッフに直接尋ねることができ、安心感が変わってきます。

横田:はろここトークのようなGPS端末は、お子さんが緊急時に即座に正しいボタンを押せることがとても重要だと考えています。そのため、最初のデザインスケッチでは一目でわかるように本体いっぱいにボタンを配置していましたが、実際に作る段階でより使いやすくわかりやすいようにと調整を重ね、防水性などの設計要件やコストとのバランスも考え、現在のデザインに至りました。
“わかりやすさ”をデザインしていく上で意識したことはありますか?
横田:開発過程で中筋さんにご意見を伺う中で、「子どもが何を押したら何が起こるのかが明確であること」が非常に大事だと言われました。そこで、緑のボタンを押すと話せる、オレンジ色に光ったボタンを押すと聞ける、黄色のボタンを押すと位置を知らせられる、というように、1ボタン1機能ということを基本に設計しています。
中筋:“わかりやすさ”には僕も強くこだわって意見をしました。話し合いの中で、「ボタンを2回押す」とか「長押しする」という案も出ましたが「それはやめてください」と伝えました(笑)。 それぞれのボタンの押し方が異なるなど、操作が複雑になると混乱して使えなくなってしまう子もいますし、何よりいざという時にシンプルな動きで使える方が絶対に良いと思っていたからです。

横田:「日常生活のルールと結びつけるといい」というアドバイスもいただいて、信号機のように、緑は進め(OK)、赤は止まれ(NG)、黄色は注意のようなルールをボタンの色やLEDの光の色にリンクさせ、話したい時は緑、エラーが出たら赤、注意を促すのは黄色という色の使い方に統一するほか、音と光のデザインについても、聴覚優位、視覚優位などの違いがあっても使いやすいよう、通信できたら音が鳴る、失敗したらエラー音が鳴るという、端末の反応がお子さんにもわかりやすいようにデザインしました。
この音と光のレスポンスにも課題があり、押した瞬間に反応させるのか、通信が完了してから反応させるのかとても悩みました。即時に反応すると「押せた」と子どもが安心しますが、通信に時間がかかる場合はその間に違和感が生じてしまうため、このバランスをどう取るかは非常に苦労しました。
中筋:ボタンにはそれぞれ「マイク」や「吹き出し」などのマークも付いていて、YouTubeなどで音声入力に慣れている現代の子どもたちには、自然に理解できるデザインになっていると思います。
横田:基本はシンプルな操作に重点を置いていますが、実はより使いこなしていけるお子さん向けに2回押すことで家族を選んで連絡できるなどの隠れ機能も搭載しています。
特別なものではなく、みんなにとって使いやすいものを目指す
今回の開発プロセスを通してどのような発見と影響がありましたか?
横田:中筋さんや参加者の方にいただいた声やアドバイスをしっかり取り入れたことで、「どうしてこのデザインなのか」をちゃんと説明できる製品になったと思っています。ボタンの数や色の意味とか、語れるポイントが多く、他のものにはないアイデアが詰まっています。
今回のような新製品の開発だけではなく、リードユーザーの方にまだ試してもらっていない他の製品もあるので、今までなかった新しい視点をいただきながら改良していこうと考えています。例えば、今ある製品の違う使い方の提案などもできるんじゃないかと感じています。
中筋:正直最初は「HOWS DESIGN」のことは知らなかったのですが、横田さんと一緒にお仕事する中で知り、記事も読ませていただくと、僕たちの障がい福祉とすごく近い視点でやられているなと感じました。ただ整ったデザインではなく「障がいのある方が使いやすい=みんなにとっても使いやすい」という考え方や、お互いに補い合うという視点にすごく共感しました。なので今回参加できて本当に良かったですし、僕個人としてもめちゃくちゃ楽しかったです。
横田:これまでユニバーサルデザインやインクルーシブデザインは「特別なもの」という印象があり、障がいや特性のある誰かに合わせすぎると他の人が使いづらくなる難しさもあるのではないかと思っていたので、最初は少し不安もありました。
しかし今回は、素直に意見を取り入れて使いやすさを追求していくことでみんなにとって使いやすいものになったと感じ、こうやって意見を取り入れながら進めると本当に良いものができるんだと感動しました。
「HOWS DESIGN」の取り組みを通じて、今までは配色において色覚特性のことを意識したり、ボタンの明度差を調整したり、LEDが光ったときにどう見えるかなど自発的に取り組めたので、とてもよい影響を受けたなと思っています。

一方通行にならない関係性を作っていく
リリース後の反応はいかがでしたか?
横田:「トーク機能、待ってました!」という声も多く寄せられています。それ以外にも、ハロファミのターゲットとは違うんですが、企業さんや自治体さんから高齢者向けの見守りや緊急アナウンス用途にも活用したいという問い合わせが増えていて、広がりを感じています。これらの反応を受けて、アプリケーションの方では次のプロジェクトもスタートしています。
中筋:施設側からは、トーク機能があることで施設から子どもへのアナウンスなど一方通行ではなく双方向でやりとりできて、文字が読めない子にも音声でちゃんと伝わるから、使い方の幅が広がって嬉しいという声がありました。
これからの展望があれば教えてください
横田:ハロファミは双方向の見守り、「家族が一緒の時間を共有する」というコンセプトなので、はろここトークを持って出かけたくなるとか、家族で行ってみたいイベントをアプリで見つけて一緒に行ってみるとか、ユーザーの体験までサポートしたいと思っています。
過去には「通学できなかった子がハロファミ製品をきっかけにやってみようと思えた」という事例もありました。これからのハロファミは「子どもがやりたいことを見つけて、それにチャレンジする」、その「できた」を応援できるブランドになりたいと思っています。
今回、小学生とコラボしてはろここトーク専用の保護ケースを図工の授業でデザインしてもらったのですが、そうした子どもたちと一緒に使いたいものをつくる取り組みなども、続けていきたいと思っています。
中筋:僕らは高度な技術を持っているわけではないですし、そういうものを作れる立場でもないのですが、今回、現場で「生の声」を拾ってそれを届けるというかたちで関わらせてもらえたことで、今まで引き出せなかったお子さんや親御さんの一歩を後押しすることができたと感じています。僕自身も、家族に「これ、いいね」と言ってもらえる商品作りに携われたことはとても良い時間でした。今後もそれぞれの立場を生かしてお互いに助け合いながら、気づきを届け合いながらやっていけたらなと思っています。

取材日:2025.6.2
インタビュー:合同会社逍遥学派・中西 須瑞化
執筆:合同会社逍遥学派
撮影:合同会社逍遥学派
編集・校正:中西 須瑞化・HOWS DESIGNチーム